はじめに:相続放棄の「タイミング」で失敗するケース、意外と多いんです
宅建試験では、民法の中でも「相続」に関する問題が毎年出題されています。
その中でも特に受験生が混乱しやすいテーマが「相続放棄」。
「放棄すれば責任を回避できるんでしょ?」と思っている方、ちょっと注意が必要です。
今回は、相続放棄のタイミングが争点となった判例をベースに、「いつ、どうすれば効力が発生するのか?」を丁寧に紐解いていきます。
そもそも「相続放棄」とは何か?
財産も借金も受け継がないための制度
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切引き継がないという意思表示を、家庭裁判所に申述することで効力を生じる制度です。
その目的は主に、「被相続人が抱えていた借金を相続人が背負うことを回避する」こと。
ただし、その効力はいつ放棄したか=タイミングに大きく左右されるのです。
事例紹介:遅すぎた放棄申述、債権者の請求は止まらない
具体的な争点は「起算点」と「期限」
事例を見てみましょう。
Aさんの父Bが亡くなり、Aさんは債務の存在を知らされていませんでした。
数ヶ月後、Bの借金に関する督促状が届き、驚いたAさんは相続放棄を家庭裁判所へ申述。
しかし、裁判所の判断は以下の通りでした。
「相続放棄の申述期間(3ヶ月)を過ぎているため、相続は承認されたものとみなされ、放棄は認められない」
Aさんにとっては寝耳に水のような判決。ここで問われたのが「いつ、相続の開始を知ったのか」というタイミングの認定でした。
根拠となる民法の条文
民法第915条:熟慮期間は3ヶ月以内
この判例の根拠は民法第915条です。
民法第915条第1項:
「相続人は、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続の放棄または承認をしなければならない。」
つまり、「知った時から3ヶ月」がリミット。
この「知った時」がいつか、が争点となる場合は、実務・裁判例の認定次第で結論が分かれてしまうのです。
宅建試験で問われるポイント
選択肢に潜む「起算点の罠」に注意
試験では以下のような選択肢が出ることがあります:
- 「相続放棄は被相続人の死亡後、いつでも可能である」 → 誤り
- 「相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に申述しなければならない」 → 正解
- 「相続人が相続開始を知った日とは、死亡日を指す」 → 誤りの場合あり(判例によって異なる)
要するに、「いつ知ったか」と「どう認識したか」で答えが変わってしまう、というひっかけポイントです。
判例の解釈と実務的注意点
放棄が認められた判例もある
一方で、以下のような判例では放棄が認められたケースもあります。
– 相続人が財産も債務もないと信じていたことに合理的根拠があった – 相続人が督促状を受けて初めて債務の存在を知ったことが証明された
このような場合、裁判所は「起算点は督促状が届いた日」と認定。
申述期間内と判断され、相続放棄が認められるケースもあるのです。
実務でも、「相続人が内容を把握していたか」が重要な争点になります。
語呂合わせで覚える:「サンゴの放棄」
3ヶ月以内=熟慮期間を忘れない
民法915条の熟慮期間は「3ヶ月」。
語呂合わせで覚えるなら、「サンゴ(3・誤)放棄で命取り」。
少しダジャレ調ですが、「3ヶ月を誤ると放棄できない」という点を強調する語呂です。
試験直前の復習にも効果的です。
まとめ:相続放棄は「タイミング」がすべて
宅建試験での得点に直結するポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 民法第915条 | 放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内 |
| 起算点 | 実務では死亡日ではなく「知った日」になる可能性あり |
| 判例 | 合理的理由があれば放棄が認められるケースも |
| 試験対策 | 語句の細かい違いに注意し、条文理解を重視 |
次回予告:宅建 判例シリーズ#03「意思無能力と契約取消」
シリーズ第3弾では、契約の有効性をめぐる「意思能力の欠如」に関する判例を取り上げ、受験対策と実務知識の両面から掘り下げます。
今後も、宅建試験で得点源となる判例を、わかりやすく、記憶に残る形でご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね!

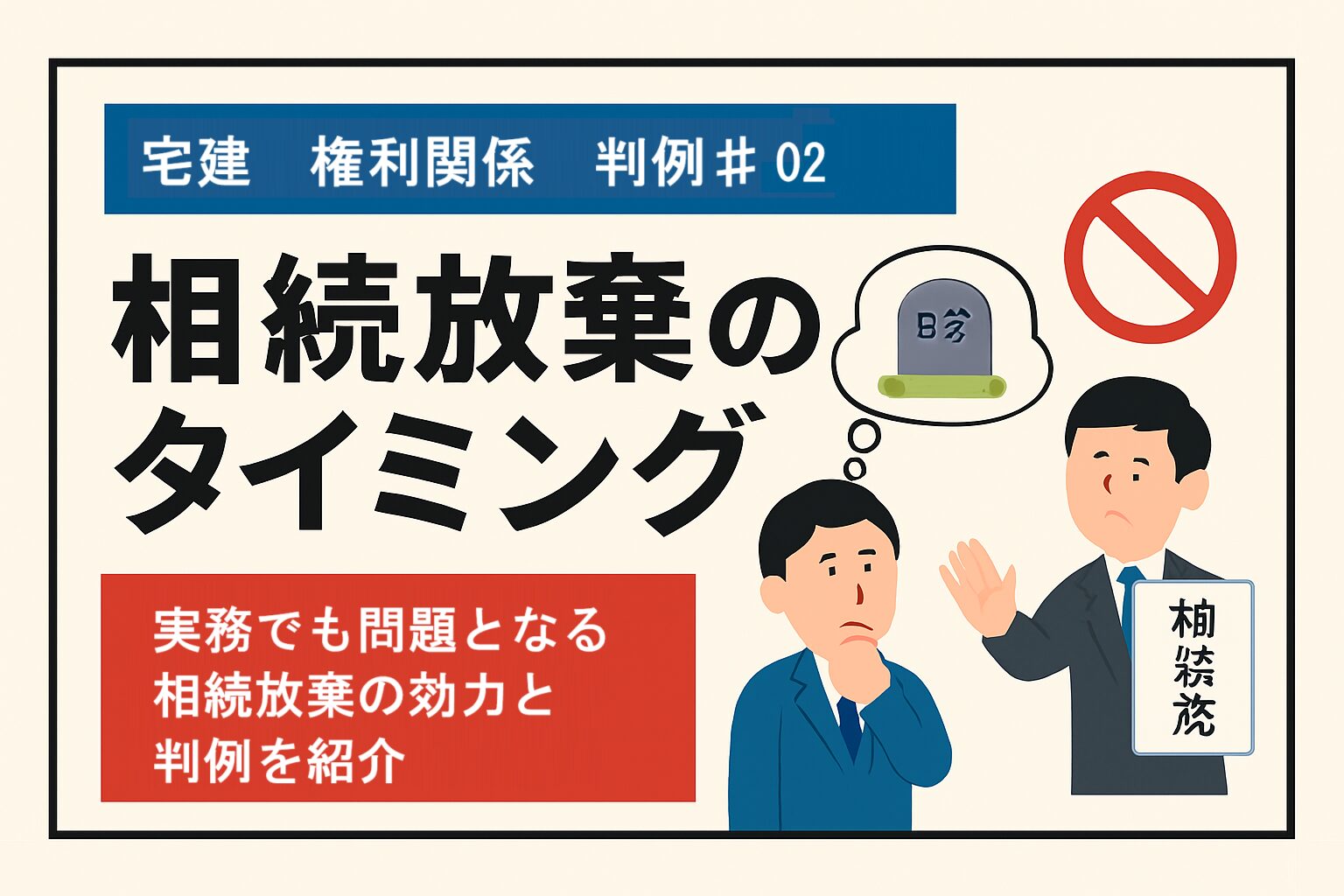
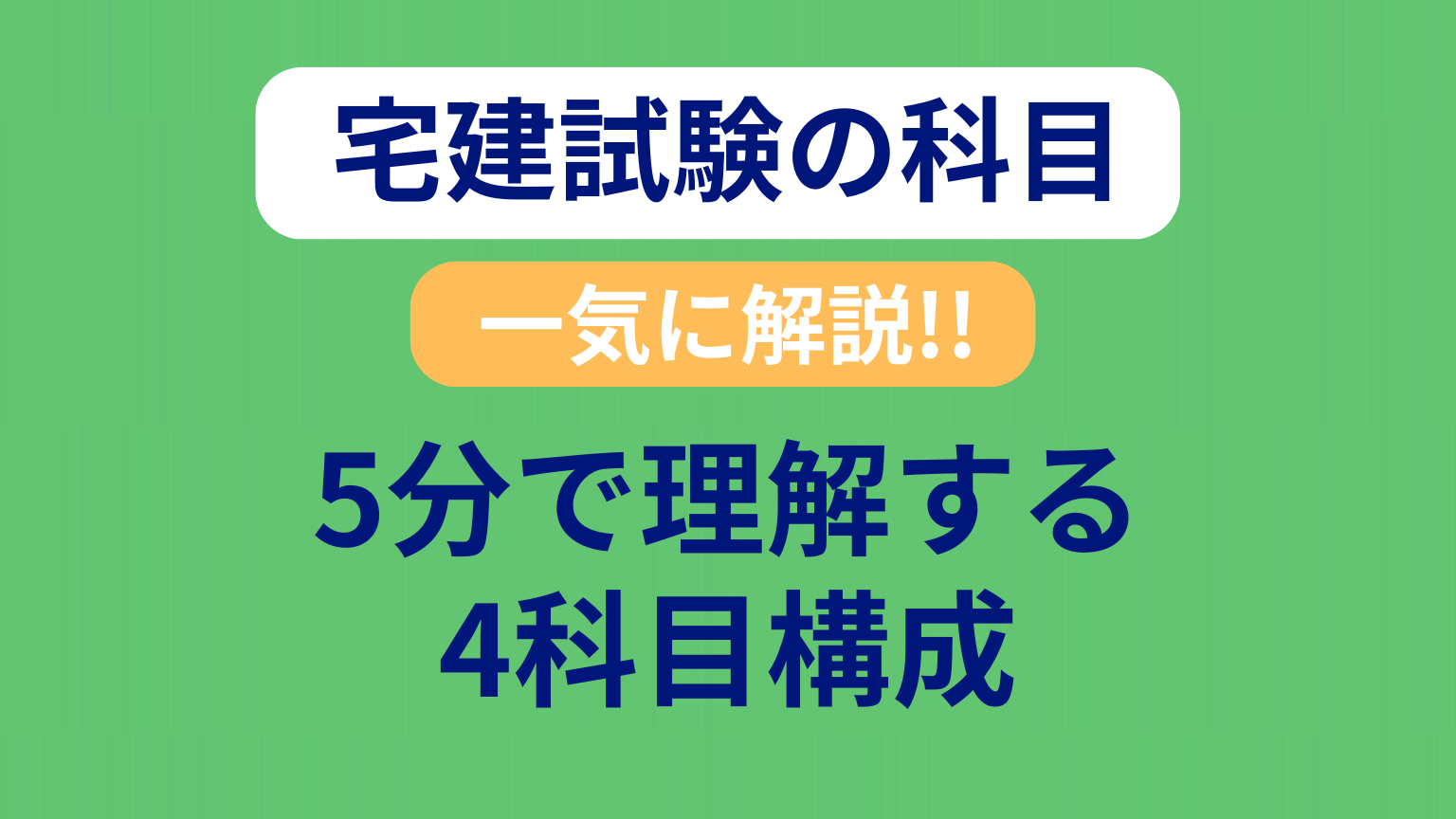
コメント